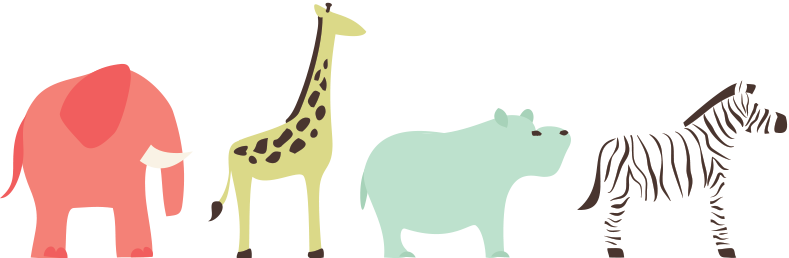以前読んだ『永遠の0』や、『風の中のマリア』でお馴染み百田尚樹。この人の本はストーリーの中に、取り上げられる題材についての解説書かと思うぐらいの詳細な記述があって、小説なのか解説書なのかどっち付かずな文章に慣れるまでは違和感があったりするけど、私も百田尚樹3作目ともなれば予備知識は十分である。太平洋戦争の神風特攻隊の物語、スズメバチの物語ときて、今回の『モンスター』は、醜い顔を持って生まれた女性が整形手術によって美人になって行くというストーリーである。
主人公は小学生時代からブサイクなことでひどく虐められ続けていた。ひょんなことからやってみた二重まぶたの手術をきっかけに美容整形にハマっていく。綺麗になるにつれて周りの男達の反応が変わっていく様がやけにリアルである。
今回は美容整形に関する施術方法や、人が「美しい」と感じる顔の形などの記述が豊富で、男の私としては大変興味深く読んだ。主人公の女性を「私」という一人称を用いて常に主人公目線で物語が進んでいくので、整形後の感動や違和感、痛みや入院期間や施術費用まで、まるで自分が整形手術をしたかのように思えて、きちんと丁寧に取材したんだろうなという印象がある。
ただ、やっぱりそこは男の筆で書かれているので、もしかしたら女性がこれを読むと、整形手術に感する情報は参考になると思うが、本当の女性の心理は少し違ったものなのじゃないかなと思った。それよりも、美人に変身した主人公を口説き落とそうとする男性の滑稽さが目立ち、思わず赤面してしまう男性も多いのではないだろうか。
ストーリー自体は淡々と進んでいく。特にどんでん返しがあるわけでもなく、あ~自分だったらここでこんな事件を用意するだろうなあなんて考えながらのところがあったが、この物語はミステリーでもなんでもなく、「美人は得をし、ブスは損をする」という社会のタブーというか常識というか、そういうちょっとグレーなところを突いた作品ではないかと思う。
個人的にはラストのエピローグはいらんかなと思う。中村うさぎの解説は秀逸。やはり美容整形に関しては、男性目線と女性目線では少し違うと思った。この作品、ヨメに薦めてみようと思います(笑)。
「読書」カテゴリーアーカイブ
『プラチナデータ』 東野圭吾 幻冬舎
舞台は近未来。凶悪犯罪における現代のDNA捜査は容疑者と証拠品が同一人物のものかどうかを確認するだけのものだけど、この物語の舞台ではさらに進化していて、性別、身長、体重、体型、肌の色、足のサイズ、髪の量、持病など様々なデータを読み取ることができるようになっている。さらにそのデータを解析してモンタージュ写真を作ることができ、しかもその容疑者の血縁関係者をも検索することができるという時代。
とある殺人事件が起こり、いつもの様に犯人が落とした髪の毛からDNAデータを解析すると、なんと解析者本人のDNAだった。追う側から一転して追われる側に立場が変わってしまうという、まるでハリウッド映画のようなストーリー。まさかと思って調べてみたら、やっぱり映画化されてたのね。何度も言うようだけど、最近の売れっ子小説家は、映像化されることを前提にしてるようにしか思えない。私のような読書初心者にとっては脳内で映像が描きやすいので助かる面もあるけど、本が売れないこのご時世、映像化して2段階で儲けたろという下心があるのではないかとやらしいことを考えてしまう。
ひとつの事件がやがて大きな陰謀へとつながり、物語は意外な方向へと進んでいく!……ことはなく、まあ主人公にとっては意外な方向かもしれないけど、読者にとっては予想できる展開と言えないこともない。協力者の現れ方もどこかの映画でみたことあるように思うし、真犯人の意外性もあんまりないし、たくさん散りばめられる伏線のまとめ方が、最後の方で無理くり根性包みしたような印象も若干ある。なんだか先に映画化されてる作品を小説化したような感じが否めない。
電トリ、ハイデン、NF13、Dプレート、モーグル等、この物語の中だけの単語がたくさんあり、作者のアイディアの豊富さには素直に感服する。ここ最近の東野圭吾作品のほとんどは映像化されている。私は東野圭吾が好きなのでなるべく原作本を読むように心がけているが、これだけ映像化されたものがヒットするということは、原作が映像化するに持って来いの素質があるからであり、もうちょっと言うたら、東野圭吾を楽しみたいなら映像化されたものを観るだけでええんちゃうかという気にもなってくる。
せっかく飲酒量を減らして家事育児の隙間を縫って読書に充てる時間を捻出して読んでいるのに、ボケーっと観てるだけで東野圭吾に触れた気になってしまう映像化にはちょっと賛成しかねる。時間をかけて読書してる者が損した気分になってしまうのは私だけだろうか。なんか感想文というより愚痴みたいになってしまったけど、そんなことを考えながら読み進めてたのは事実。ちょっと読むジャンル変えてみよかな…。
『とんび』 重松清 角川文庫
現在TBS系日曜日夜9時からやっているテレビドラマの原作。元々猛禽類が好きなので(笑)、このタイトルはドラマ化される前から本屋に行った際に目に付いていた。ところが内容は猛禽類のトビとは全く関係なく、「とんびが鷹を生む」という言葉からタイトルが付けられ、父と子の感動ドラマであるという。ちょっとこのテの物語は今はええかな…と敬遠していたのだが、テレビドラマ化されるとあって、「映像化反対派」の私としては、こりゃ早く読んでおかないと損をするかもなということで購入。
舞台は昭和37年から始まる。不器用で真面目で破天荒で情に厚いヤスさんが主人公。昭和の物語にはよく登場する典型的な“頑固オヤジ”である。そのヤスさんに待望の男の子が生まれるも、奥さんを事故で亡くしてしまい、周りの協力を得ながら男手ひとつで子供を育て上げるヤスさんの生涯を描くお話。もうそれだけで目頭が熱くなる要素が満タンである。
本の構成は12編あって、1話毎にヤスさんとその息子のアキラが成長していく過程で起こる様々な問題や出来事などを感動のエピソードで締めるというふうになっており、まさにドラマ化するには最高の原作である。最初からドラマ化を目指して書いたのではないかと思うぐらいに一つ一つのお話が綺麗にまとめられていて大変読みやすい。
文章も堅苦しい表現や、回りくどい描写などほとんどなく、わかりやすい文章だった。登場人物のキャラクターがハッキリしているので、細かい人物描写や心境などをダラダラ書かなくても、脳内でキャラクターが簡単に想像できる。それぐらい『とんび』に登場する人物は親しみやすい。
だから感情移入がハンパではなく、物語の中にスッと溶けこんでいける気がする。ヤスさんは時折矛盾したり意味不明の言動があるのだが、「わかるわかる」となる。ヤスさんが笑えばなんだかコッチも笑えるし、ヤスさんが怒ればコッチもなんだかカッカしてくる。そしてヤスさんが泣けば、コッチもぽろぽろと涙が出てくる。
ストーリー自体はベタである。アキラが生まれてから小学校、中学校、高校、大学、就職、結婚…と成長する。謎解きがあるわけでもなく、ラストにどんでん返しがあるわけでもなく、読み進めると展開があらかた予想できてしまうぐらいベタなんだが、それがいい。“泣かせどころ”も「はいはいまた来ましたか」というぐらいベタなんだが、わざとそれに引っかかるぐらいの軽い心構えで読むといいと思う。
子育て世代のパパにおすすめ。ただし、電車通勤される方は読まないほうがいいかも。涙が止まりません(笑)。
『忍びの国』 和田竜 新潮文庫
久しぶりの読書感想文。全く本を読んでいなかったというわけではないんだけど、たまたま短編集ばかりだったので感想文を書くのが億劫だっただけ(笑)。この本は本屋をブラブラしているときに偶然見つけた本。今話題になっている映画『のぼうの城』の原作者ということで平積みにされていたのが目に留まった。
この物語は実際にあった「天正伊賀の乱」が舞台になっている。伊勢に本拠地を置く織田信長の次男信雄軍と、百地三太夫率いる伊賀忍者軍との戦いを描いた歴史アクションもの。初めのうちは登場人物の名前を覚えたり人物の相関を想像したりするのが大変だったけど、スピーディーな展開で全く飽きなかった。歴史モノはあんまり手に取ることは無かったのだがこれからはこいういうジャンルにも手を伸ばそうかなと思える作品だった。
“忍者”といえば、運動神経抜群で走りがめっさ速く、ジャンプ力があって忍術も使えるという、子供にとって嫌われる要素が全く無い正義のヒーローだったのだが、物語の忍者はそう甘くない。平気で人を殺すし仲間を裏切る。金のためになんでもやる、最低最悪の悪党である。そんな殺人マシーンのような忍者の中にもやはり人間味を帯びたやつが何人かいて、そいつらが物語のキーになってくる。
歴史の通りに最終的には伊賀忍者は織田軍に滅ぼされてしまうのだが、織田家の家臣の一人が「伊賀者の血は滅びてはいない。私利私欲のためにだけ生きるその精神は、いずれ子の代孫の代と天下の隅々までに浸透するだろう」と言う。このセリフが本当かフィクションが知る由もないが、現世の人間を揶揄した作者のメッセージなのだろう。一見ハチャメチャな痛快忍者アクション物語も、このセリフでビシッと締めくくられたようだ。
ネットでも書評なんかを読んでいると、『のぼうの城』も面白かったということなので読んでみようと思う。ともあれこの作品はオススメです。
『1Q84 BOOK1~3』 村上春樹 新潮文庫
この本がTVニュースなどで話題になったのはつい最近のことだと思っていたけど、2009年に発売されたとのことなのでもう3年も経ったんだなあと改めて月日の流れの早さに驚く。BOOK1からBOOK3まで、3冊もの超長編(少なくとも私にとっては)が文庫化され、それぞれ上下巻合計6冊となって再販された。BOOK1~2までの上下巻4冊はうまい具合に古本屋で見つけることができたが、BOOK3の上下巻2冊は新品を買った。古本を含むとは言え、一つの物語に2500円前後の大金と、6冊分の読書エネルギーを使ってようやく読み終えた。
世界中で翻訳されてヒットしている本なので、改めてここであらすじを説明する必要もないと思う。私の解釈としては、青豆さんと天吾くんの純愛ミステリーということだろう。そこに宗教やらパラレルワールドなんかが重なってきて、ものすごい広い世界観になっている。今まで何冊か村上春樹の作品を拝読したことがあって、どれもこれも掴みどころが無いというか、明確な解答が無いというか、村上春樹ファンの言葉を借りるならそこには「喪失」しか感じられなくて、どうも肌に合わなかったのだけど、この『1Q84』に関しては「まだマシ」と思える。
丁寧すぎる顔立ちや容姿の描写、音楽やその他芸術に関する詳細な記述、スマートで無駄のない台詞など、まるで伊坂幸太郎を読んでいるような印象だった。でもそれは村上春樹が伊坂幸太郎を真似したのではもちろんなくて、伊坂幸太郎は思いっきり村上春樹に影響されているんだなあと感じた。ていうか結構そこまで真似していいんやねと思ったぐらいである。
ストーリーは非現実的で不思議な方向へだんだんとシフトしていき、いかにも!な村上春樹ワールドへ突入していく。以前の経験から、しっかり読み込んで謎を解けば解こうとするほどワケがわからなくなるという教訓を基に、不思議ちゃんな部分はさらりと読み流す方法でなんとか頁を進めることができた。もっと単純に、もっと素直に、「なかなかすごい比喩やなあ~」とか、「そろそろ濡れ場があってほしいなあ」とか考えながら。
後で知ったことなのだが、実は『1Q84』はBOOK2までで終わりだったそうだ。確かに1と2は同時発行だけど、BOOK3だけは約1年後の発行である。この事実を知ったのはちょうどBOOK3を読み始める頃だった。私は3まであるもんだという心構えで2を読み終えたから良かったものの、もしBOOK2の「あの」シーンで終わりですよと言われたら暴れていたかもしれない。「村上春樹どんだけ~~」である。どんだけ読者に喪失感を与えたら気が済むねんと。
しかし敬虔なる村上春樹信者は文句も言わず、「そうか、春樹さんがここで終わり言うんやから終わりなんや」と受け入れた。もしそうだとしたら、村上春樹の信者になるには相当の「スカシ」にも耐えられる精神力を持たないといけないということである。とにかく村上春樹は約1年というブランクを空け(ワザとだったのか苦情が殺到したのか知る由も無いが)、BOOK3で広がり過ぎた世界をまとめにかかった。そのまとめ役が牛河氏である。
BOOK3は牛河氏のお陰でだいぶ読みやすかった。青豆と天吾を追う探偵役として登場するのだが、2人の過去を洗い直してくれるお陰で、忘れていた背景などを思い出すことができ大変助かった。牛河氏がいなければ、私は未だ釈然としない『1Q84』の世界から抜け出せず、もう二度と村上春樹は手に取らなくなってしまったかもしれない。もしかしたらBOOK3は編集社が強く希望したから完成したのではないかと思うほどのハードルの低さになっていた。それだけ私に貢献してくれた牛河氏はなんとも悲惨な最後となるわけなんだが、6冊(1冊約400頁弱)もの村上春樹ワールドにどっぷり浸かってしまった私は、「はいはい何があっても驚きませんよ」ぐらいにスルーすることができたのである。
6冊である(ひつこい)。6冊もの文庫本が本棚に並んだら結構場所を取るぜ。期間にして約2ヶ月半(読むの遅い)。そんな長い時間村上春樹に触れていると、あの独特の文章にもっと長く触れていたいという気にもなってくる。物語は佳境を迎え、残り頁が少なくなってくると若干の寂しさみたいなものが感じられた。これを信者が言う「喪失感」なのだろうか。物語が終わって感じる喪失感とはなんだか違う心のポッカリ感がある。別に無くても生きていけるけど、無いと寂しいような物足りないような……。
ともあれ、今までは「投げっぱなし感」の強かった村上春樹の作品だったが、この『1Q84』ではだいぶ解釈がしやすかった。村上春樹側が私に合わせてググっとハードルを下げてくれたお陰なのか、はたまた私が月の2つある世界に脚を踏み入れてしまったのか。とあえずまだ1つしか見えない。
『ナミヤ雑貨店の奇蹟』 東野圭吾 角川書店
小遣い制のサラリーマンであるが故にいくら読書好きでもそうそう書籍にお金をかけるわけにもいかないので、新作が出ても文庫化されるまで待つか、ひどい時には古本屋に並ぶまでその作品そのものを忘れ去ろうと努力するタイプなのだが、どこの本屋の前を通っても平積みされてるわ、「本屋スタッフのオススメ!」みたいに飾られてるわ、どうやっても忘却の彼方に追いやることができそうにもなかったので、半分諦め半分ウキウキで1600円という超高級な本を手に取ることにした。
でも後悔はなかった。読んでみて内容が大変良かったというのももちろんあるけど、夏目漱石や芥川龍之介などならともかく、今をときめくバリバリの人気作家の最新作品というものは、その本自体が生きているような感じがして私のようなビンボー読者には新鮮であった。物語の中には「スマホ」とか「東日本大震災」などの比較的新しい単語や話題も出てくるし、本の内容と自分自身がリンクしているような感じは今まで古本を漁っていた頃にはなかった感覚で、そういう意味でもこの本はとても楽しめた。
さて、あらすじ。空き巣をやらかしたバカな男3人が身を隠すために偶然転がり込んだあばらやがナミヤ雑貨店である。しばらく息を潜めていると店先のシャッターの郵便入れに手紙が入れられる。不審に思いながらもその手紙を開けてみると何やら人生相談が。面白半分に返事を書いて裏の牛乳ポストに入れるとお礼の手紙がすぐさま届く・・・。
3人が飛び込んだナミヤ雑貨店の浪矢さんはかつて、町の人々の人生相談の手紙をやり取りしていたことが話題になり地元ではちょっとした有名店であった。しかしそれは30年以上も昔の話。当時おじいさんだった浪矢さんは当然亡くなっており、ナミヤ雑貨店にも誰も住んでいなくて埃まみれ。それなのに届く相談の手紙。ナミヤ雑貨店で起こるタイムスリップ現象に巻き込まれる3人の不思議な体験を描くSFファンタジーである。
大きく分けて5編で構成されており、それぞれナミヤ雑貨店に相談する人物は違うのだが、後半に行くにつれ登場人物の過去と未来が絡まりあって、実に見事に組み立てられて完成されていくのは流石という感じ。つい先日『苦役列車』を読んだばかりだったので、物語の美しさにうっとりするぐらいだ(笑)。いや別に『苦役列車』が作品としてあかんというわけではないが、例えば嫁さんとか子供などに勧めるならば、断然『ナミヤ雑貨店』である。
タイムスリップを題材にした物語は多数あるが、この作品のように一見バラバラに見える複数の登場人物と複数のエピソードを、最終的に一つの時間軸にまとめるのは難しい。アラを探せば幾つかのパラドックスが見つかるかもしれないが、そこはわからんように整理されてて綺麗にまとまっている。実に数学的というか物理的というか、とにかくきっちりしている印象がある。もう少しアバウトな部分があってもいいかなとも思うけど、そこは作者の性分なのだろうかちょっと説明くさい所もある。
実は東野圭吾にはタイムスリップする作品がちょくちょくあって、パッと思いつくのは『時生』である。主人公の息子が未来からやってきて色々と人生のアドバイスをするというストーリー。未来からの指示通りに行動して成功する流れなどはこの作品に良く似ている。さらに後半に登場する女性のビジネスにおける成功は『白夜行』や『幻夜』に登場した雪穂にも似ていて、東野ファンにとっては嬉しいポイントではないだろうか。
おまけに、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』にも似ている部分がある。それは感動のラストの場面なので詳細は控えるが、“あの”シーンのオマージュであると感じた読者は私だけではないはずだ。私はこの映画が大好きなのでこのラストはとても嬉しかったし感動した。
人生のターニングポイントに人は悩み、憂う。だけど決めるのは自分だ。未来の自分から、あの時の選択は正しかったよと声が聞こえるならば、どれだけ楽なことか。せめて過去の自分に「正しかったよ」と言ってあげられるような人生を送りたい。
この本はかなりオススメです。本屋の気持ちがわかった(笑)。
『苦役列車』 西村賢太 新潮社
久しぶりに読書感想文。この作品はいつか読みたいなと思っていた。先日本屋に行った際に映画化されるということで平積みされ私の目につきやすい場所にあったのと、思いがけず薄っぺらい(頁が少ない)本だったのですぐに読み切れるだろうということから手に取った次第。
北町貫多という19歳の青年が主人公。日雇いで稼いだ金はすぐに酒と風俗につぎ込み、安普請のアパートの家賃を滞納し追い出され、食うや食わずの自堕落な生活を送るという最低最悪なヤツである。やがて日雇いの仕事で知り合った日下部という青年と仲良くなるのだが、これもまた元来のヒネクレ精神により仲違いしてしまう有様。
私小説とのことなのでこの貫多が著者であると考えてよいのだと思うが、私ならこんなやつとは決して友達にはならないだろうなと思いながらも、自分のことだけに貫多の心情や描写がやけにリアルで、軽い嫌悪感と同時にちょっとした共感もあったりする。
決して貫多には同意も肯定もしないのだが、なんだか不思議な魅力があって、そこはやはり誰もが他人に対して持っている劣等感であったり、他人より優位に立っていたいという浅ましさであったりが共通するするからであろう。日々の社会生活の中でフタをしている自分のダークな部分があからさまに書き出されているようで気持ち悪くもあり清々しくもある奇妙な感じだ。
同じ19歳でも『ノルウェイの森』のワタナベ君とはドエライ違いである。ええとこの子供で衣食住と学業とセックスには困らない19歳と、片や性犯罪者の息子で風呂にも入らず毛布一枚で寝起きする風俗通いの19歳。見かけは全く異なるが、しかし根底に流れる原動力みたいなものは実はおんなじで、今この歳になって思い返してみる自分の19歳の頃にも似ているのではないかと思う。
ちなみにこの文庫本には、『落ちぶれて袖に涙のふりかかる』という短編も併録されているがこちらも私小説で、貫多が40歳を越えて売れない小説家となった自分自身を描いている。小説家という稼業とそれを取り巻く編集者や読者を、自分の気分の落ち込みや盛り上がりにまかせて揶揄するなど、私個人的にはこちらのほうが好きだった。
巻末の石原慎太郎の解説にもあるが、芥川賞を獲り、映画化も決まり、かなりの大きな金と名声を手に入れた“貫多”に、今後この手の小説が書けるのかどうか他人事ながら心配になる。それらを手に入れた上でまた以前と変わらぬ貫多が登場すればこの作家の実力は本物である。おそらく元来のヒネクレ精神により、貫多は一生満たされることはないのだろうと思う。だから安心して次の貫多を待ちたい。
映画版の予告をチラ見してみたが、主人公の貫多を演じるのは『モテキ』でモテにモテた森山未來である。しかもヒロインには前田敦子である。原作には貫多が片思いするような女性は出てこない。何が言いたいのかと言うとキレイすぎるのである。『苦役列車』はこんなもんじゃないと、映画を観るつもりもないのにエラソーなこと言ってみる。
『風の歌を聴け』 村上春樹 講談社
村上春樹初心者の私が手にとった2作目はデビュー作。村上春樹を無理に好きになろうとはしていないが、前に読んだ『ノルウェイの森』ではきちんと理解できなかったという惨敗感が残ってしまったのは事実。デビュー作なら入口にはちょうどいいかなという理由と、薄っぺらくてすぐに読めてしまいそうという理由と、古本屋で安かったからと理由で選んだ。
大学生である主人公のひと夏の経験を語り綴ったもので、なんだか『ノルウェイの森』に似ている。特にきっちりとしたストーリーはなくて、主人公が鼠という友達とジェイズ・バーで飲んでいるかと思ったら急にラジオのDJが喋りだし、そしてまた急にデレク・ハートフィールドの話題になったりする。自由である。まるで酔っているときに思いつくままに書いたような感じ。
こんな読者のことを無視して自分のやりたいよいうにやっている作品のどこがいいのかわからないが、ついつい引き込まれてしまうこの魅力はなんだろうか。
私はミステリーが好きで色々と読んだ。ミステリーはきちんとしたストーリーがあって、謎が隠されてて、登場人物たちが絡みあって、そして最後に全ての謎が解かれる。まるで最終的に解答がきちんと用意されている数学みたいなもんだ。問題に取り組んでいるときは必死だし引き込まれるし時間が経つのを忘れる。
村上春樹をそんな心構えで読むと必ず失敗する。明確な解答がないのに必死で問題を解いたって解きようがない。裏切られる。それこそ酒を飲みながら、何も考えずにただ文章に目を通すような読み方でいいのだろう。必死に紐解いてみてもそこには答えはないし、そんなことをするのはそもそもダサいことなのかもしれない。
「読書」と言うと、当然のことながら「文字を読んで物語を理解する」ということになろうが、もっと自由でええねんなと思う。ミステリーは一度読了するとストーリーもオチもわかってしまっているから再読する気にはなかなかなれないけど、こういった作品は、いろんな気分の時にいろんな場所で何度も読むのがいいかもしれない。コートのポケットに入れておいて、5分でも時間が空いたらペラペラと頁をめくる。ミステリーではまとまった自由時間とシラフな頭脳を用意してからでないと楽しめない。
この本は、私に新しい読書のやり方を教えてくれた気がする。本のオススメ度なんかを★の数で評価するのはダサいんだなということも。
『レイクサイド』 東野圭吾 文春文庫
やっぱり800頁オーバーの文庫本を持ち歩くのは重い。厚さ1cmか2cmぐらいのもので持ち運びが便利な本を…と探しているうちにコレが目に留まった。以前読んだ『午前0時の忘れ物』でも湖が出てきたのでなんかの縁かなと思って。
湖の畔にある別荘へ中学受験の集中合宿にやってきた4組の親子と塾の講師。なんとかして有名私立中学に合格させたい親たちは必死になって我が子をサポートするが、なにかそれ以上の結束の固さに違和感を感じる主人公。そんな中殺人事件が起こってしまうが、それすらも異常なまでの結束力で隠蔽してしまおうと力を合わせる親たち。違和感を感じながらも我が子を守るために隠蔽工作に力を貸していくが、ある秘密に気付く。
都会から離れた別荘地で起こる殺人事件。主な登場人物は4組の家族。なんだかベッタベタなミステリーである。こんな場面に子供探偵やらマヌケ刑事やらが登場して「犯人はあなただ!」みたいなことになれば、某人気アニメのパクリに決定~となるところだが、そこは東野圭吾。探偵も警察も登場しない(探偵役みたいな人は登場するけど)。
加熱する受験戦争への批判を織りまぜたなかなか面白い物語だった。非常にテレビドラマ的な展開で、すぐにでも映画化できそう。いやもうとっくになってるんだが。途中の隠蔽工作においてちょっと説明臭いところがあってシラケるけど、最後のどんでん返しがいかにも親バカって感じで良い。★★★★☆でした。
『白夜行』 『幻夜』 東野圭吾 集英社
再読。東野圭吾では最も素晴らしい大作として評価されるこの2作。『幻夜』は『白夜行』の続編か否かということでファンの間で論議されることがあるが、私の個人的な意見としては、「そりゃ続編やろ」と思う。でもまあこの2作品が続編であるか否かなんて、それこそまさに重箱の隅をつっつくようなもんで、独立した2つの作品と見たとしてもそれぞれが読み応えのある壮大なストーリーとなっている。
『白夜行』は男女2人の幼なじみが、自分たちの犯した罪をひたすら隠蔽していく。それらが非常に巧みで、罠にはめられていく登場人物も多種多様。よくこんな展開が思いつくなあと感心する。舞台はオイルショックの頃の大阪から始まり、阪神タイガース優勝であるとかスーパーマリオ発売であるとかバブル崩壊であるとかに進んでいく。その舞台と時代背景が、私自身が今に至るまでの時代と完全にかぶるので、そういう意味でも物語にものすごく引き込まれていく。
特徴的なのは、幼なじみの2人である「雪穂と亮司」が文中ではほとんど顔を合わさないことである。電話で会話するシーンもない。2人が様々な事件を隠蔽していくにあたって、間違いなくどこかで相談なり作戦会議なりをしているはずなのに、そういう部分が一切でてこない。それが逆に2人の絆を強く表現していて、間違いなく犯罪を犯している2人に対してなんだか同情する気持ちも芽生えてしまう。同情というか、ものすごいことをやってのけるスーパースターを見てるような感じかな。尊敬するみたいな。
『幻夜』のストーリーも大まかには同じで、男女2人が自分を守るために罪を重ね、それを巧みな裏工作で切り抜けてゆく。ところが『白夜行』と違うのは、完全に男が女に操られているところである。前作とは違って男女はしょっちゅう顔も合わすし会話もする。男は女に決定的な弱みを握られていて、それを隠し通すために女に協力することを約束するのだ。
続編かどうかを決定するのは、『白夜行』で登場した「雪穂」が、『幻夜』で登場する女「美冬」が同一人物かどうかにかかってるわけだが、文中にはそれを決定付けるものは何もない。たぶんそうやろなー程度のもので確定ではない。読者の想像に委ねられる部分である。共通点はたくさんあるので同一人物と考えてほぼ間違いないと思うけど、あまりにも雪穂と美冬の性格やら言葉数が異なるので、単純に同一人物にしてしまうのは違和感があるのも事実。でも最初にも書いたように、同一人物であるかどうかがこの物語のメインではない。
両作品に共通するのが、なんかこの女は怪しいと勘付いて独自に捜査を始める人間がいること。物語が進むにつれて核心に迫っていくのだが、とにかく非常に悲しいラストが待っている。涙が出るとかそういう悲しさじゃない。女に尽くす男の末路に言葉をなくすし、自分の人生の為なら女はここまで冷徹になれるのかと思う。両作品とも「惚れたもん負け」みたいなところがある。
すでにドラマ化や映画化され、そちらの方もなかなか評判が良かったようなので、機会があれば観てみたい。両作品とも当然★★★★★でした。