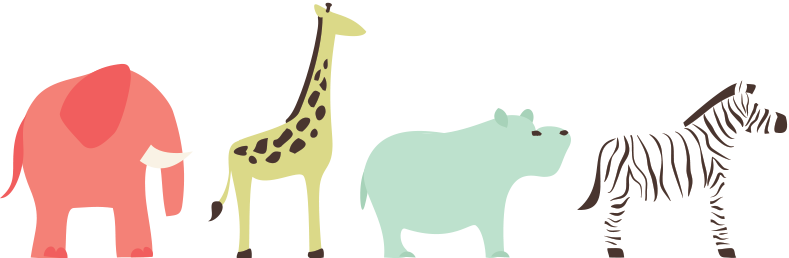本屋に平積みで展示してあったので手に取った。新作というわけではないし、改めてなんかの賞を獲ったというわけでもなさそうだけど、本屋が勧めるなら読んでみよかと。
高速バスが湖に転落して多くの乗客が死亡。残された遺族や恋人たちは心にポッカリと穴の開いたような日々を過ごしていたが、事故から1ヶ月後、死者からのメッセージが遺族や恋人たちに送られ、深夜のバスターミナルに集合。そこで繰り広げられる不思議な出来事を描くファンタジー小説。
素敵なお話だった。もちろんありえないことなんだが、生きることの切なさとか人を愛することの素晴らしさなんかが描かれていて心が暖かくなる。
……な~んて背表紙のあらすじみたいなこと書いてちょっと赤面するわ。自分なりに感じたことを書く。赤川次郎は他にも何作か読んだけど、この人の作品には若い女性がメインになることが多いのかな。若い女性が好きなエロオヤジなんかなと思ったけど、セリフの短さとかテンポとかがほんとに若い女性が会話してるかのようなリアルさがあって、もしかしたら赤川次郎がオネエじゃないのかとさえ思う。ファンの方すいません(笑)。
ちょっと前に小説に登場する若者って言うことが理路整然としてて語彙が豊富なんてことを書いたけど、それはやっぱり作者によって違うんやなと思った。赤川次郎はとてもシンプルなセリフばかりで小気味良い。セリフの後に「と、法子は言った。」とか「と、恵は言った。」という書き方が多くて、そこだけを意識して読んでると小学生の作文みたいに思えるのだが、それがまったく違和感なくて、文章を文章として読んでいるのではなくて、文章をまるで映像のように眺めていくような感じ。
だからページにも余白の部分が多く、とても早いペースでページが進んでいく。登場人物の数もちょうど良くて、舞台もほとんどが実ケ原バスターミナルで終始するのでとても読みやすい。中学生とかが読んだらええんちゃうかな(笑)。★★★☆☆でした。
「読書」カテゴリーアーカイブ
『歪笑小説』 東野圭吾 集英社
読書感想文が続きますよ~(笑)。
さて、今年の1月25日に第1刷が出たばっかりの「◯笑小説シリーズ」の最新版。怪笑小説とか毒笑小説とかがあって、これは「わいしょうしょうせつ」と読む。「歪笑」なんて言葉はないと思うけど、読んでみるとほんとに口元がニヤリと歪むような笑いが起こる。いつものような本格ミステリーではなくて、コミカルな短編集です。
出版社と小説家との裏を暴露するような笑い話が12編あってお腹いっぱい。でも短編集とはいえ、それぞれのお話しの中で登場人物やシチュエーションは繋がっていたりしてたいへん楽しめる。小説家になりたいなーなんて妄想したことはあるけれど、やっぱりどこの世界も大変なんだなと思う。
超売れっ子作家である東野圭吾自身が出版社の内部を暴露するなんてちょっとずるいなあと思ったりもする。そらあんたが書いたらおもろなるわみたいな。ここに登場する「灸英社(きゅうえいしゃ)」とは明らかに「集英社」のパロディであり、ハチャメチャな編集長とか売れない新人作家など、きっとモデルになる人物がいるのだろうけど、「東野さんに書かれたら仕方ないよな~まいっちゃうな~」であろう。
「面白さが不謹慎さを圧倒的に抜いたからこそブラックジョークが成立するんだ!よほどのセンスがない限り手を出さないほうが賢明だ!」なんてツイートがあるけど、ほんとに東野圭吾はセンスに溢れてる。本格ミステリーも書ければ短編も書けるし、そんな才能に感心しながら読み進めたりすることもある。なんか完璧すぎて怖い感じもする。どれを読んでもハズレがなくて失敗しない。
だからこそ、誰も知らない売れない新人作家の作品の面白さを探してみたいと思うこともあるわな。そう思えるようになってきたら私も読書中級者かな? 熱海圭介の『撃鉄のポエム』は読んでみたい(笑)。★★★★☆でした。
『砂漠』 伊坂幸太郎 新潮社
天気が思わしくないので自転車にも乗らず読書してばっかりな日々。まあ晴耕雨読という言葉もあるぐらいだから、有意義な毎日だということにしておく。
さて、にしやんオススメの伊坂幸太郎『砂漠』。5人の大学生が送る青春のキャンパスライフを描く。「プレジテントマン」と名付けられた通り魔とのあれこれとか、賭けボウリングでのあれこれとか、超能力のあれこれとか、連続空き巣犯とのあれこれとか、色々と大学在学中に起こる事件に巻き込まれていく。
正直言うて一件一件の事件は物語全体を揺るがすようなビッグなものではなく、厳しく言うたらしょうもないことばっかりなのだけど、登場人物5人のキャラクターが際立っているので飽きさせず、とっても爽やかである。
特に西嶋くんってヤツがぶっ飛んでて、かなり好きなキャラクターである。ていうかこれを読んで西嶋くんのことが嫌いになるやつはおらんだろう。この小説は西嶋くん無しには有り得ない。西嶋くんに笑わされ、西嶋くんに泣かされ、西嶋くんに感動する。そして、主人公の北村くんはなぜか『ノルウェイの森』のワタナベくんとかぶる。鳥瞰的に物事を見るところとか、冷静なセリフとか、そしてきっちり彼女作ったりして適度にモテてるところとか、なんか似てると思った。
小説内に登場する19・20の若者って、理路整然と物事を理解し、豊富な語彙できっちりと話すし、ボキャブラリーもとても広くて歌の歌詞とか物語の一説を引用したりする。そしてそれを利用して相手を説得したり納得させたり…。特に伊坂幸太郎作品にはそういう場面が多い。熟考を重ねて登場人物にセリフをしゃべらせるわけだから当然といえば当然だけど、実際にこれだけ話せる人間っているのだろうか。
カーっとなったときはついつい何をしゃべってるのかわからんようになるし、自分の考えを相手に伝えたいときも言葉が出てこずに「あーなんて言ったらいいかなー」ってなることが多い。アラフォーの私でもそうなるのに、ノルウェイでも砂漠でも、19歳の若者はどんな場面でも落ち着いてて、聞いてて(読んでて)惚れぼれする。これぐらいしゃべれたらゴネ客にも対応できるのになーなんてね。
まあちょっと重箱の隅をつつくようなことばっかり書いてしまったけど、とにかく学生時代の“オアシス”から、社会という“砂漠”に出るための5人の成長記のような物語です。私は大学には行かなかったし、麻雀もスプーン曲げもできないので共感できる部分は少なかったけど、カツカレーとか牛丼みたいな食べ応え満載の東野圭吾作品ばっかりではコレステロールも溜まるので、たまにはこういう野菜スープみたいな作品もおもしろいなと思う。★★★★☆でした。
『どちらかが彼女を殺した』 東野圭吾 講談社
久しぶりの東野圭吾である。ネットなどの書き込みで予備知識はあったのでそれほど戸惑わなかったが、やはりそれでも最後まで犯人がわからんというのは違和感がある。腹八分目ならいいけど、腹七分目ぐらいの感じ。そんで本の最後に犯人特定の鍵となる袋とじ解説が付いている。最終的な謎解きは読者に委ねられるという前代未聞の推理小説である。
自殺に見せかけて殺された妹を、兄が独自で犯人を追求していくというストーリー。兄は犯人が特定できれば復讐をしようと心に決めていたが、そんな悲しい復讐は阻止しようとするのが東野圭吾ではおなじみの加賀恭一郎。お互いはお互いの推理で容疑者を絞り、最終的には確定するわけだが、推理小説にはお決まりの「犯人はお前だ!」のところで、犯人が誰か教えてくれない意地悪なラストなのだ。
謎解きが大好きな人にはたまらんだろう。名探偵コナンなんかでも最後の犯人特定のシーンの直前にCMに入ったり、来週に持ち越したりするけど、その間に自分なりの推理を考え巡らせる人と、さっさと犯人教えてスッキリさせてくれよ~という人に分かれる。完全にこの作品は前者向けである。私はめんどくさがりなので後者である(笑)。
前者の中には犯人特定の袋とじ解説を開かずにもう一度読み返す人がいるだろう。私もすぐに答えを見てしまうのはなんだか悔しいので最初からもう一度読み返し、そこらじゅうに散りばめられた伏線を再確認していったのだが途中で断念した。「なにやってんの!?」とヨメが聞いてくるのを無視してハサミでザクザクと切った。小説にためらいもなくハサミを入れている私を見てヨメはさぞかし不思議に思ったであろう。
とはいえ、謎解きを読者に委ねるために登場人物を少なくしてあり、非常に読みやすい。時間の流れもほとんど時系列に流れて行くので混乱せずに一気に読むことができる。読むのが遅い私としては、一冊の文庫本を読み切る時間としては最速とちゃうかな。★★★☆☆でした。
ちょっと話変わるけど、本文中に推理小説を揶揄するような部分が出てくる。「現実には推理小説のような事件は起こり得ない」などとある。時刻表トリックとか密室とか怪しい洋館とか山奥の小屋とかダイイングメッセージとかがばんばん登場する推理小説を書いている東野圭吾本人が、まるで照れ隠しのように自らの作品を揶揄するセリフを作中の登場人物に言わせるのだ。
東野圭吾作品の中には『名探偵の掟』など、自分が用いてきた、ミステリーには不可欠な手法(密室とかダイイングメッセージとか)を自らこき下ろして面白おかしく書いている作品も多い。これは関西人特有の性格なのではないかと思う。
ふざけたことを言って笑わせたり、真面目なことを言って感動させたりするのは好きだけど、心のどこかで「これは冗談やで~」みたいな余裕というか冷めた部分というか、そんなとこを自ら残しておくことに美学を感じているのではないだろうか。一人が大真面目にセリフを言ってるのに、もう一人が現実に戻して笑いを誘う、漫才のボケとツッコミにも似たような関係にあると思う。東野圭吾は自らの作品の中で、ひとりでボケとツッコミをやっているのだ。同じ関西出身者としてなんかとても共感できる部分である。だから好きなのかもしれない。
『友へ-チング-』 郭景澤 金重明 文春文庫
次は何を読もうかと思い巡らしながらも本屋に行く機会がなかなか無く、なにげに自分の本棚を漁っていたら出てきた本。『シュリ』と共に韓国で大ヒットした映画の小説版。実は『シュリ』の小説版も持っていて、何を隠そう私は『シュリ』の大ファンである。こちらのほうは映画も観たし小説版も何度も読んだ。ところが『チング』に関しては全く記憶が無い。本は持っているのに読んだかどうかの記憶が無い。じゃあ読んでみるかと手に取った次第。
4人の幼なじみのそれぞれの成長の過程を描き、それぞれの境遇で苦悩しながらも固い友情で結ばれているよ、というストーリー。半分ぐらいは原作者の実話で、当時を思い起こして描いている。スタンド・バイ・ミーみたいな感じかな。まあそんな爽やかな内容ではないけれど。もともと映画で大ヒットした作品なので、やはり小説にするとパンチ力が弱い。私の記憶に残らないのもムリはないと思った。どうしても『シュリ』と比べてしまうかな。『シュリ』は派手なアクションシーンや切ない恋愛が描かれていて、いかにもハリウッド的なエンターテイメントだったが、こちらはそういう派手さはない。
でも、男の固い友情が底辺にあるので泣き所は多い。4人の中でも一番ケンカが強くてリーダー格だった奴が、大人になって麻薬に溺れヨレヨレになっているところを、4人の中で一番弱かった奴がおんぶして家に帰るというシーンがある。ケンカに負けて泣いている自分をおぶってくれた奴を、大人になって逆におんぶするという切なさに2人が泣くのだが、もらい泣きする。この本での泣き所はほとんどがもらい泣きである。
我々日本人の韓国人に対する印象って人によっていろいろあると思うけど、なんか熱いよね。私はそう思う。すぐに感情がむき出しになるっていうか、日本人だって温情に溢れてるけど、韓国人のそれはハンパない感じがする。この小説にはおもくそにそれを感じる。ハリウッドに慣れた日本人は『シュリ』の方が合っていると思う。だけど韓国人には『チング』の方が合っているのかな。韓国では『シュリ』や『JSA』を抜いて『チング』が観客動員数を上回ったということでも証明されている。
でもまあこれは小説。映画で成功したからって小説にしても成功するとは限らない。逆のパターンもしかり。★★☆☆☆でした。
『風の中のマリア』 百田尚樹 講談社
『永遠のゼロ』を読んでからすっかり百田尚樹ファンになってしまった。この人の作品は、取り上げられる題材(『永遠のゼロ』では太平洋戦争、本作においてはスズメバチ)をやたら詳しく解説してあるので、読了後はそれらのことについての知識が身に付く。かと言って眠たくなる参考書や歴史書ようなものではなく、しっかりとしたストーリーの中でのことなので、それほど違和感なく自分のボキャブラリーが広がるのだ。
というわけで、本作はスズメバチが題材。ていうか主人公。スズメバチの中のワーカー(働きバチ)であるマリアちゃんの物語。スズメバチの巣の中は(一時期を除いて)全てメス。女の帝国である。ワーカーはオスと恋をすることもなく、当然卵を産むわけでもなく、命を賭けて女王バチを守り、幼虫達のエサを狩猟する。そんな本能に突き動かされる自分の運命を、時に誇りに思い、時に疑問に感じる、そんな女の子の物語となっている。
スズメバチをはじめ、登場する全ての昆虫が擬人化され、もちろんセリフもしゃべるし物思いに耽ったりする。殺される直前には命乞いもする。だけど『みつばちマーヤの冒険』とか『バグズライフ』みたいにデフォルメされているわけではない。“おもくそ虫!”である。この手の作品は珍しいのではないだろうか。虫が嫌いな人はきっちりと嫌悪感を示すだろうし、シーズンになるとスズメバチと格闘しておられる某アニキにおいてはリアルにその黄色と黒のギラギラしたボディを思い出し、憎々しさで読み進めることができないかもしれない。
百田尚樹にはこのような作品が多いそうだ。まだ読んでないけど、日本初のボクシング世界チャンピオンの話や多重人格障害者の話などもあるみたい。おそらくそれらも半分小説で半分解説書。予備知識がなければ「なんじゃこれ?」みたいに思うかも知れないが、私も百田尚樹のお陰で太平洋戦争のことに詳しくなったし、スズメバチのことにも詳しくなった。知ってます?働きバチって最後に女王バチを殺すんですよ~。知らんかったな~。
ここまで持ち上げといて言うのもアレだが(笑)、『風の中のマリア』においてはちょっとストーリーの部分が弱かったかな?いかにもスズメバチの解説です!って場面が前に出過ぎてるとこがあって、物語の世界にふけってしまいたい自分としてはちょっと興ざめするとこもあったのは事実。百田尚樹を読むときはその辺の心の準備が必要だとわかった。ちょっと厳しめで★★★☆☆でした。
『ノルウェイの森』 村上春樹 講談社
恥ずかしながらこれまで『ノルウェイの森』を読んだことがなかった。確か私が高校生ぐらいの頃、CDシングルやらアルバムやらテレビ視聴率やらのランキングを発表する番組があって、書籍売上ランキング部門で何週も第1位に居座り続けた作品がこれだった。その頃は「へ~」ぐらいにしか思わなかったが、赤と緑の本はなんだか不思議と自分の記憶の中に残っていた。
ここ数年で読書が好きになっていろんな作品を読んできたので、いつかは『ノルウェイの森』も読まないとな~と思ったけど、なんか機会がなくて今に至っていた。きっとたくさんの人がこの本を読んだだろうし、読書好きな友達に言えば貸してくれるだろうし、古本屋に行けばたくさん売っていることも知っていた。別に敬遠していたわけでもあまのじゃくなわけでもないけど、なんだか読まずにいた。まあこういうモンはタイミングである。そしてそのタイミングがやってきただけのことだ。
この稀有なタイミングを大事にしたいと思ったので、私はわざと、友達に借りるとか古本を買うとかせずに、大型書店で新品を買った。超有名作家の超有名作品である。本気で向き合わないと失礼じゃないかなと思ったからだ。赤いシンプルな装幀の上巻を読み始めた時、なんか緊張してるなと感じた。まるで普段は着ることのない一張羅を着て、普段は入ることのない高級なレストランで、さあ今から食事をしようかという感じである。
で、正直に—–ほんとこんなこと言うの恥ずかしいけど—–感想を言うと、「ようわからん」。やはり高級レストランの味は私にはようわからんかった。この作品は何度も何度も読み込んで、舌が肥えてからでないと深く理解出来ないのではないかと思う。
高級な料理を、理解しよう理解しようと思いながら食べるのもひとつの食べ方だし、ただ単純にお腹がすいててたまたま目の前に高級料理があったという食べ方でもいい。私の場合はカッコつけて前者でいこうと思ってたけど、やっぱり後者でいくことにした。そしたら急に読むペースが上がってすらすらと読めた。上下巻合わせて約600頁の長編をたった2日半で読んでしまった。
「なんじゃい、ワタナベ君のモテ期日記かい!」なんて気分で読んでるといい。エロいシーンを二度三度読み返し、ノルウェイの森をギター1本で弾いたらどんな感じなのか想像し、精神病ってどんなんかなーと思いながらでいい。テーブルマナーなんか気にせずに、好きなように開き直って食べたらお腹いっぱいになりました、でいいと思うし、そういう食べ方をした自分を褒めたい。
誰しも19や20の頃は混沌としていた。将来とかセックスとか学業とか、いろんなものがごちゃまぜになって洗濯機の中でぐるぐると混ぜられて、なんやわからんうちに取り出されて干されて風にさらされ時間が過ぎ去っていった。それを40手前になってあの頃を思い出し、文章に出来る人が小説にしました。それだけの解釈でええんちゃうかと思う。今は。何年後かに読んだらまた味わいも変わるだろうし。そんなタイミングを静かに待ちたい。だからこの赤い本と緑の本は、輪ゴムでくくって大切に保管しておきたいと思う。
個人的にはレイコさんが好き。レイコさんのギター聴いてみたいな。
★★★☆☆でした。また何年後かには評価が変わるでしょう。
『ゴールデンスランバー』 伊坂幸太郎 新潮社
にしやんのオススメ。まずはこの作品を紹介してくれたにしやんに感謝。とても楽しく読むことができました。おおきに。
首相暗殺事件の濡れ衣を着せられた30台男性が、巨大な陰謀に飲み込まれながら逃げ回るというストーリー。どこにでもあるハリウッド映画みたいな内容だが、大きく分けて5部で構成されていて、さらに登場人物目線でコロコロと場面が変わり、しかも10年前にさかのぼったり現代に帰ってきたりと読んでいて飽きない。
いろんな場面といろんな時代においてたくさんの伏線が張られ、物語が進むにつれてそれらが丁寧に包まれていく。あとがきには「張り巡らせた伏線を丁寧にまとめるのが自分の作風だったがそれもつまらないので、ある程度は読者に任せる形で適当に包みました」という感じのことが書かれているけど、いやいや十分丁寧ですよと言いたい。
先日読んだ『グラスホッパー』でもナイフ使いの殺し屋が出てくるけど、『ゴールデンスランバー』にも切り裂き魔が登場する。前回も思ったけど作者はナイフで人を切る描写がとても巧い。切ったことあるんちゃうかと思うぐらい。で、心の底から腐りきった殺し屋じゃなくて、ちょっと感情移入できる殺し屋だったりするのも特徴。
登場人物の会話が同じ文字数で書かれているところがちょくちょくあり、活字をビジュアルで美しく見せてるところも芸が細かいなあと思う。最後に参考にした文献やら協力してくれた人を挙げて感謝の意を表明しているところなんかも丁寧やな~って思う。
自分の中で、東野圭吾の『白夜行』越えたかも。文句なしの★★★★★でした。
『グラスホッパー』 伊坂幸太郎 角川文庫
伊坂作品2作目。『重力ピエロ』の次に何いこかな~と思ってたら、なんかのランキング上位にこの作品が発表されたので、ミーハー気分で手に取った。妻を殺された男が復習を誓って闇の業界に転身するも、「押し屋」と呼ばれる殺し屋に先を越されてしまい、アララ~と言うてる間に他の殺し屋が出てきてストーリーが展開していく。
主たる3人の登場人物それぞれの目線で物語が進んでいき、物語が進むにつれて合流するというやり方。ちょっとハードボイルド系。人が死んでいく様が非常にリアルに描かれているけど不思議とグロさはなくて、今までに殺した人の亡霊に悩まされたりする人間味に溢れる殺し屋もいたり、雇い主に使われるままの自分に苦悩する殺し屋にちょっと同情してしまったりするとこもある。
人の身体が破壊されるリアルな描写や、『重力ピエロ』のとき感じたけどセリフとセリフの間に人物の内面を挟んだりするお陰で、読んでいて脳内での映像化が容易である。東野圭吾もそうだが、「お前これ映画化狙ってるやろ~」と、やらしい気持ちになってしまう(笑)。
自分と同世代の作家って、テレビで育った世代だからそうなるのは仕方のないことなのだろうか。もっと昔の作家、例えば夏目漱石とかは、脳内で映像化するとかそんなんじゃなくて、なんていうかな~、読んでても音楽を聞いてる感じというか、「読む→映像化→解釈」の流れじゃなくて、「読む→解釈」と言う感じ。脳内映像化の必要がない。ないというか、せんでも読めるというか…。ワカルカナー。
別に脳内で映像化することが悪いことと言ってるわけじゃなく、私もモロにテレビ育ちなのでその方が楽でありがたいぐらいなのだが、読書を一つのゲイジュツとして楽しむとするならば、やっぱり昔々の作家さんのほうに軍配が上がるんかなーと思う。東野圭吾とか伊坂幸太郎は現代っ子向け。自分もその例に漏れず現代っ子なのでスッと読める。「夏目漱石読みます」となったらなんか心の準備がいるやん?クラシック聴く前みたいな。
まあちょっと横道にそれたけど、これはこれで面白かった。個人的には「蝉」が好きかな。ちょっとおまけで★★★★★でした。
『重力ピエロ』 伊坂幸太郎 新潮社
初の伊坂幸太郎。どの作品だったか忘れたが、東野圭吾の作品の解説を伊坂幸太郎が書いてて、いつかこの人の作品も読んでみたいなあ~と思ったのが手に取ったきっかけ。
辛い過去を背負った兄弟が、連続する放火事件のルールを解明していくミステリー。謎解き自体は単純で、犯人も中盤ぐらいでわかってしまうぐらいだが、兄弟の愛が爽やかで、それでいて鼻につくわけでもなく、好感が持てる。
他の伊坂幸太郎の作品を読んでみないとわからないけど、セリフの途中に、仕草の描写を挟んで、さらにセリフを続けさせるってところが、登場人物の性格とか性質がよくわかるように工夫されている。逆に言うと読者に考える余地を与えないというか、キャラクターの顔や体格の想像が、それ以上膨らまないように制限をかけられているような感じ。まあそれは人によって好き嫌いが分かれると思うけど、何も考えずに読み進められるので楽っちゃあ楽かな。
あと、チャプター分けが細かいので、ついついそこで読むのを休憩してしまい、500頁程度の文庫なのになかなか読了出来なかった。まあ伊坂幸太郎に罪はないけど(笑)。★★★☆☆でした。