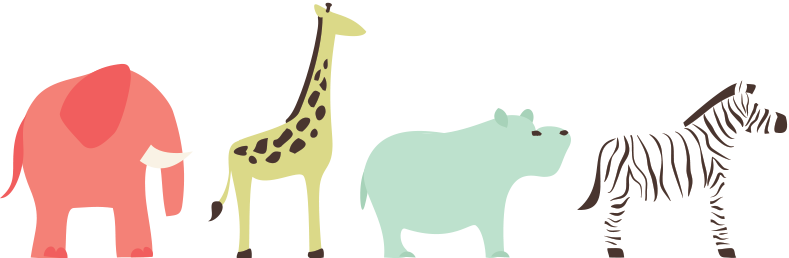久しぶりの東野圭吾である。ネットなどの書き込みで予備知識はあったのでそれほど戸惑わなかったが、やはりそれでも最後まで犯人がわからんというのは違和感がある。腹八分目ならいいけど、腹七分目ぐらいの感じ。そんで本の最後に犯人特定の鍵となる袋とじ解説が付いている。最終的な謎解きは読者に委ねられるという前代未聞の推理小説である。
自殺に見せかけて殺された妹を、兄が独自で犯人を追求していくというストーリー。兄は犯人が特定できれば復讐をしようと心に決めていたが、そんな悲しい復讐は阻止しようとするのが東野圭吾ではおなじみの加賀恭一郎。お互いはお互いの推理で容疑者を絞り、最終的には確定するわけだが、推理小説にはお決まりの「犯人はお前だ!」のところで、犯人が誰か教えてくれない意地悪なラストなのだ。
謎解きが大好きな人にはたまらんだろう。名探偵コナンなんかでも最後の犯人特定のシーンの直前にCMに入ったり、来週に持ち越したりするけど、その間に自分なりの推理を考え巡らせる人と、さっさと犯人教えてスッキリさせてくれよ~という人に分かれる。完全にこの作品は前者向けである。私はめんどくさがりなので後者である(笑)。
前者の中には犯人特定の袋とじ解説を開かずにもう一度読み返す人がいるだろう。私もすぐに答えを見てしまうのはなんだか悔しいので最初からもう一度読み返し、そこらじゅうに散りばめられた伏線を再確認していったのだが途中で断念した。「なにやってんの!?」とヨメが聞いてくるのを無視してハサミでザクザクと切った。小説にためらいもなくハサミを入れている私を見てヨメはさぞかし不思議に思ったであろう。
とはいえ、謎解きを読者に委ねるために登場人物を少なくしてあり、非常に読みやすい。時間の流れもほとんど時系列に流れて行くので混乱せずに一気に読むことができる。読むのが遅い私としては、一冊の文庫本を読み切る時間としては最速とちゃうかな。★★★☆☆でした。
ちょっと話変わるけど、本文中に推理小説を揶揄するような部分が出てくる。「現実には推理小説のような事件は起こり得ない」などとある。時刻表トリックとか密室とか怪しい洋館とか山奥の小屋とかダイイングメッセージとかがばんばん登場する推理小説を書いている東野圭吾本人が、まるで照れ隠しのように自らの作品を揶揄するセリフを作中の登場人物に言わせるのだ。
東野圭吾作品の中には『名探偵の掟』など、自分が用いてきた、ミステリーには不可欠な手法(密室とかダイイングメッセージとか)を自らこき下ろして面白おかしく書いている作品も多い。これは関西人特有の性格なのではないかと思う。
ふざけたことを言って笑わせたり、真面目なことを言って感動させたりするのは好きだけど、心のどこかで「これは冗談やで~」みたいな余裕というか冷めた部分というか、そんなとこを自ら残しておくことに美学を感じているのではないだろうか。一人が大真面目にセリフを言ってるのに、もう一人が現実に戻して笑いを誘う、漫才のボケとツッコミにも似たような関係にあると思う。東野圭吾は自らの作品の中で、ひとりでボケとツッコミをやっているのだ。同じ関西出身者としてなんかとても共感できる部分である。だから好きなのかもしれない。