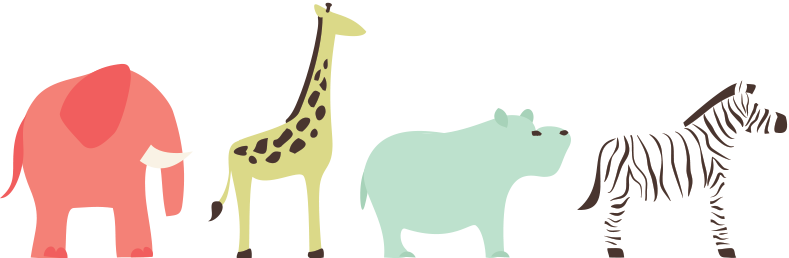伊坂作品2作目。『重力ピエロ』の次に何いこかな~と思ってたら、なんかのランキング上位にこの作品が発表されたので、ミーハー気分で手に取った。妻を殺された男が復習を誓って闇の業界に転身するも、「押し屋」と呼ばれる殺し屋に先を越されてしまい、アララ~と言うてる間に他の殺し屋が出てきてストーリーが展開していく。
主たる3人の登場人物それぞれの目線で物語が進んでいき、物語が進むにつれて合流するというやり方。ちょっとハードボイルド系。人が死んでいく様が非常にリアルに描かれているけど不思議とグロさはなくて、今までに殺した人の亡霊に悩まされたりする人間味に溢れる殺し屋もいたり、雇い主に使われるままの自分に苦悩する殺し屋にちょっと同情してしまったりするとこもある。
人の身体が破壊されるリアルな描写や、『重力ピエロ』のとき感じたけどセリフとセリフの間に人物の内面を挟んだりするお陰で、読んでいて脳内での映像化が容易である。東野圭吾もそうだが、「お前これ映画化狙ってるやろ~」と、やらしい気持ちになってしまう(笑)。
自分と同世代の作家って、テレビで育った世代だからそうなるのは仕方のないことなのだろうか。もっと昔の作家、例えば夏目漱石とかは、脳内で映像化するとかそんなんじゃなくて、なんていうかな~、読んでても音楽を聞いてる感じというか、「読む→映像化→解釈」の流れじゃなくて、「読む→解釈」と言う感じ。脳内映像化の必要がない。ないというか、せんでも読めるというか…。ワカルカナー。
別に脳内で映像化することが悪いことと言ってるわけじゃなく、私もモロにテレビ育ちなのでその方が楽でありがたいぐらいなのだが、読書を一つのゲイジュツとして楽しむとするならば、やっぱり昔々の作家さんのほうに軍配が上がるんかなーと思う。東野圭吾とか伊坂幸太郎は現代っ子向け。自分もその例に漏れず現代っ子なのでスッと読める。「夏目漱石読みます」となったらなんか心の準備がいるやん?クラシック聴く前みたいな。
まあちょっと横道にそれたけど、これはこれで面白かった。個人的には「蝉」が好きかな。ちょっとおまけで★★★★★でした。