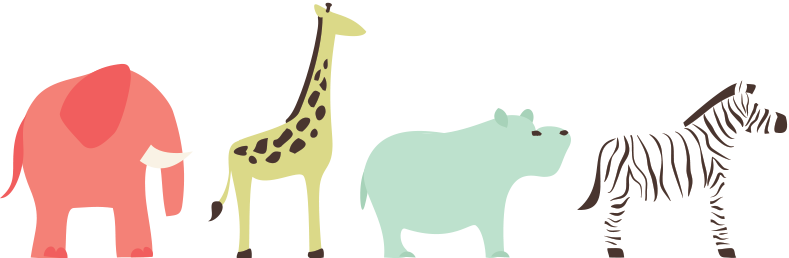関西シクロクロスのプロローグ、南山城ステージを観に高山ダムまで行ってきた。630に木馬朝練の集合場所に行き清滝をみんなで登り、りゅう吉さんとそこから離脱してひたすらR163を走る。りゅう吉さんはロードバイク、私はクロスバイク(ブロックタイヤ)だったので巡航速度の違いを懸念していたけど、怪我あがりのりゅう吉さんはリハビリライドのため2人同じぐらいのちょうど良いペースで巡航できた。
片道50kmちょっと走って高山ダム到着。すでにレースは行われている。NAMくんに挨拶して会場をウロウロ。実は生まれて初めてシクロクロスの会場に来た。ちょっとした広場をテープで区切ってコースにしている感じで、途中に斜面を利用したテクニカルな部分や、階段を駆け上がる部分、自転車を持ってジャンプする障害物などが仕掛けられている。それらを文句も言わず必死で走るシクロッサーを眺めていると、まるでタミヤRCカーグランプリに来たかのようだ。私がプロポを持ってみんなを操縦している感じ。
バイクも皆さん自分流にアレンジされていて、まさにホビー感覚が満載。特にNAMくんのワイヤレスDi2においてはその最たるもので、トップチューブ長の分をワイヤレスにすることの何がメリットなのか良くわからんが(笑)、とにかくそういうカスタムが見ていて面白い。私はとにかくクロス車を早く手に入れようとするばかり、パーツアッセンブルに何も拘らずに慌てて完成させたが、シクロクロスの楽しみを自らの手でひとつスポイルしたような残念感が否めない。
私は仕事で自動車のメカを触っているので、仕事以外で工具を触るのがあまり好きではない。そういう理由もあってあんまり自分で自転車を組むことをせずにすべて回転木馬任せであった。もちろんそのほうが結果的に早く安心して乗れるので、それ自体は別に間違った選択ではないのだが、人の手で組んだRCカーを走らせてもつまらないのと同じで、シクロクロスというものの楽しさは、もしかしたら私の考えていた場所とは少し違ったところにあるのかな、と気付いた。反省にも似た、後悔にも似た、残念感である。
とにかく走ることに楽しさを感じる人もいる。シクロクロスを楽しんでいる人の中には当然自転車なんて自分で組めない人もきっといて、それでも楽しそうなんだから、きっと楽しいものなのだろう。私は今日は観戦のみだったのでそういった走るほうの楽しみはわからなかったが、きっと走れば楽しいはずなんだ。今日は走ってないから残念感があるんだ。などと自問自答しながら、観戦しつつも心ここにあらずと言った感じで、実はそこにいるのがちょっとしんどいぐらいだった。
私はやっぱりメカいじりが好きなんだなと思った。「乗れば楽しいよ」って人は言ってくれる。だけど私は、所謂「スポーツ」としてだけでなく、パーツ選びや自分流カスタムにも自転車の楽しみがあると思っている。元来ストイックにトレーニングしたり同じことを地道に続けたりすることが苦手な私がここまで自転車を続けてこれたのは、自転車にはイジる楽しみがあったからだったのだ。もう一度初心にかえって取り組みたいと思う。それぐらい、初のシクロクロス観戦は私に影響を与えてくれました。
同行してくれたりゅう吉さんどうもありがとうございました。NAMくんもお疲れ様。感謝です。
肩痛い

もうクロス車は通勤車ということでいいんじゃないかという思うほど通勤ばっかり。今日も清滝ショートカットでつづら折れから直登の階段コースへ突入。
担ぎがヘタなのかなんなのか、肩が痛すぎる。そもそもBMCは担ぐことなんて何も考えてないようなフレームの形状をしてるので余計痛い。痛い痛いと思いながら担いでいると偶然スイートスポットを発見し、そこにハマると自転車が軽く感じるから不思議。
最近「シクロクロスを楽しむ」というよりも、「オフロードを楽しんでいる」という感じ。これならMTBでええがなと冷静な自分が登場しそうなときもあるが鉄の意志で封印。ファジーなブレーキ、窮屈なポジション、ノーサスの乗り心地…。コレがええねんやんけと言い聞かせる。
ミッキー&ミニー弁当

小さめのおにぎり2つに大粒のぶどうが4つってのはどうなんやろ?と思いながらも適当な食材が見つからなかったのでOKとする。ミニーのリボンはカニカマをカットしただけだが、もうちょっと凝っても良かったかなと思う。なんせミッキーとミニーの違いはまつ毛とリボンの有無のみ。
子供の成長と共にキャンバス(弁当箱)が小さくなってきた。大きめの弁当箱に移行するのは構わないが、その分作品が大きくなりすぎるという懸念と、空白を埋めるおかずのレベル向上が急務となるので、そろそろキャラ弁からは卒業したいのがパパの本音。幼稚園を卒園したら当然幼稚園の先生との接点もなくなる。誰を喜ばせるためなのか目標を見失うので(笑)。
秋雨前線(?)の影響によりお休みしていたシクロクロス通勤も今朝再開。いつもの秘密のトレイル(秘密でもないが)を走っていたら、奥の茂みから大きな動物が飛び出してきた!
なんと見知らぬローディー。いや、シクロッサー。ディープリムにチューブラーのブロックタイヤを履かせているあたり、かなり屈強なシクロッサーとみた。『ディープリム=屈強』というイメージが払拭できない。あまりに唐突だったので写真どころか挨拶もできなかったが、みんなシクロクロスシーズンに向けて始動しているんだなあ。
エントリーフィーも安いのでいろんなレースに出場したいが、なんせ日曜休みは貴重。家庭の様子を伺いながらできるだけのことはしたい。
ノーベル京橋賞
iPS細胞を作成したカシコの人がノーベル賞をGETしたという話題が紙面を賑わせている。関西人でユーモアのセンスがあり、マラソンが趣味で今度の大阪マラソンにも出場するということで、特に関西圏において好感度抜群である。
もうすぐ文学賞の発表もあるそうだが、こちらはご存知村上春樹氏が有力なんじゃないかというハナシである。今朝の『す・またん!』(関西ローカルの朝の情報番組です)で、「村上春樹の作品でどれが一番好きか」というアンケートを行なっていた。場所は京橋。
村上春樹作品を理解できる人間が京橋をウロウロしているとは思えない。案の定、
「あ、ああ~、角川春樹ね。えっ?違う?あれやろ?イチキューマルヨンのやつやろ?あれ正直難しいわ~。途中で止まったままやねんガハハ」
というオッサンがいて私は大変安心した。しばらく京橋には行ってないが、昔と変わらず京橋は京橋のままだった。さらに約7割の人が「読んだことない」という回答であり、これで向こう5年は京橋の平和は約束されたと言っても過言ではない。
しかし中には、「透明感があるから好き」とか「展開がワクワクさせる」などというカシコな回答もあって私をヒヤリとさせた。しかし顔を見れば明らかに京橋の人間ではない。おそらく京都辺りのセレブが、京阪からJRに乗り換えて芦屋に住む娘夫婦のところに遊びに行くという感じで、京橋はただの通り道だったのではないかと推測する。こういう人達は、是非これからも京橋はスルーして頂きたい。カシコのエキスで京橋を汚して欲しくないと思う。
京橋は、ええとこである。
走破性
700Cのシクロクロス車でダートを走っていると、26インチのMTBよりも走破性がいいのでは?と思うことがある。私がロードにばっかり乗っている間に、MTBの世界は29インチが主流になりつつあるようで、フレームとタイヤの大きさのアンバランスさに「なんだかな~」と思っていたけど、やはり大きなホイールは悪路には大変有利なんだなと感じる。
MTBのときにやっていた「フロントの抜重」を、少々サボっても軽々と走り抜けてくれることがある。まだ不慣れなシクロクロス車のドロップハンドルではタイミング良くハンドルを引き上げられなくて、仕方なしに「ええ~い、いってまえ~」みたいな感じで大きめの石や段差に突入しても、意外と車体の挙動を大きく乱すこともなくクリアできる。
あと、今朝初めて数段の階段を乗車したまま降りてみた。サスペンションがないから確かに衝撃はあるけど、変にスコスコとフロントフォークにストロークされないからコントロールしやすいなと思った。
色々と考えながら乗れるからオフロードは面白いね。
清滝ショートカット

シクロクロス通勤も早3日目。昨日は土砂降りに見舞われてしまい、朝からズブ濡れになってしまったがそれもまた一興。シクロクロスはライダーの懐までも深くさせてしまう。今朝は打って変わって秋晴れの爽やかな天気。清滝峠を普通に登っても面白くないので、ショートカットコースに入ってみる。
つづら折れの途中から頂上までを直登するような道。もともとハイキングコースのためにほとんどが階段。以前からこの道は気になっていたのだが、ほとんどが階段であることは知っていたので、いつかシクロクロス車を手に入れることがあったら自転車を担いで駆け上がってみたいなあと思っていたのである。
しかしまあしんどいことしんどいこと。駆け上がるなんて夢のまた夢である。よくよく考えたら、「自転車を担ぐ」なんてことは明らかに正しい行為ではない。それは自転車そのものの存在意義を根底から覆すものであり、人類の行動範囲を効率的に広げようと一生懸命に自転車を発明し開発した先人の行為を侮辱するものである。簡単に言うと、
「何やっとんねん」
である。しかし一般人から見れば理解不能なことであれ、それをしばらく続けていると脳内からオカシナ物質が分泌されて、無性に楽しくなってくるもんである。これをお読みの諸兄にもわかって頂けると思う。謂わばヘラヘラ状態。おそらくこの同時刻に、兵庫にも京都にも滋賀にも金沢にも、同じ状態の人間が無数にいるのだろうなと思いを馳せると、ヘラヘラは収まるどころかますますエスカレートしていく。
ひさしぶりに山の中で笑ったなあ。
シクロクロス!

BMC CX02。NAMくんからフレームと各種パーツをわけてもらい、回転木馬で足りないパーツの買い足しと組立てをお願いして完成した。皆さんどうもありがとうございます。早速今朝、通勤の足として(笑)デビュー。
特に軽量パーツなどに拘らなかったのでやはり重い。持ち上げた感じはMTBぐらいあるんじゃないかというぐらい。これを担いで階段を登ったり段差を飛び越えたり、もはやこの時点でウンザリ感が否めない(笑)。と同時に、いつも乗ってるC59は本当に軽いんだなと再認識する。気を取り直して走りだす。
走行して一番に感じるのはフロント周りのねっとり感。タイヤとホイールが重いせいかハンドリングが非常にマイルドである。平坦な舗装路では慣性力が働いて思いのほか高速巡航が可能だが、当然のことながら峠を登るとその重さが現実的に表れる。
少しタイヤの空気を抜いて通勤途中のダート道に入ってみた。やはりオフロードは、自転車がどうこうとかそういうのは抜きで楽しい。小石や折れた枝を弾く音が小気味よくて、ついつい遠回りをしてしまった。もうすこし軽いギヤがあればいいかなと思ったけど、レーシングな場面ではこれぐらいがちょうど良いのだろう。オフロードをのんびりツーリングするバイクではない。本来の目的を見失わないようにしなければ。
初めてスラムの変速機を使用してみたが、まだまだ慣れるには時間がかかりそう。とくにフロントの変速はコツが要りそうだ。レース中の小パニックな場面で確実に変速するにはもっと練習が必要だ。
ともあれ新しいオモチャを手に入れたパパは機嫌が良い。これからも事故や怪我に気を付けて乗り込んでいきたい。
コルナゴC59

洗車したのでパチリ(#^o^#) やっぱりコラムのデベソはカットしよう。
C59に乗り始めて1年半。C50の次はC60だろうと思っていたらC59だった。C59はC60までの繋ぎ役モデルで忘れられる日も早いんだろうなと思っていたけど、デビューして未だにコルナゴのフラッグシップモデルとして君臨し続けている。いろんなカラーバリエーションが登場してるけど、正直コルナゴのカラーデザインはあんまりカッコイイとは思えない(^^;) イタリアンかクラシカルかのどっちかという印象。昔に比べたら塗料も安っぽいのかな。私のC59は蛍光イエローの部分に紫外線による色あせが出てきた。
ともあれ私には勿体無いぐらいの性能でよく走ってくれる。踏めば応えてくれるので、自分の調子の善し悪しがハッキリ表れるそんなバイク。これからも永く乗っていきたい。間違いなく私の宝物のひとつ。
パンクのたびに思う
今朝通勤途中に清滝頂上付近でパンクした。最近山間部に入ると大きめの石が落ちていることが多いように思う。避けきれずにリヤタイヤが乗り上げてプシューである。交換したばかりのソコソコお高いチューブラーだったので非常にもったいない。辟易しながらスペアタイヤに交換してリスタート。
リム両面テープもところどころにしか残らず、ハンドポンプでは高圧まで入れることもできず、会社までの残りの道のりはペースも調子も上がらずテンションの低いまま走ることになる。シルキーな乗り心地が気に入ってチューブラーを使い続けているが、パンクするたびに通勤メインの私がこんなに不便で不経済なタイヤを使い続けていいものか悩んでしまう。
安いチューブラーもあるにはある。しかしすぐに摩耗してしまうし、それによってパンクの回数も多いように思う。紫外線によるひび割れも早い段階で発生するし、ひどいモノは真円が出ていなくてずっと変なバイブレーションのまま回転する。せっかくいいフレームといいホイールを使っているのでタイヤをケチりたくはないという気持ちもあるし、いやいや庶民は庶民のタイヤで十分!という自分もいる。
いっそのことクリンチャーかチューブレスにするという手も思い付くが、ホイールを手配する初期投資が当然必要だし、結局のところパンクしたときの面倒臭い度合いは変わらないのではないかとも思う。自転車通勤にはパンクは付き物であると割り切って、パンクがイヤならクルマに乗れよという、至極当たり前な考察結果に約30分ほどかけて到達した。毎回のことである。
会社に着いて、工業用石鹸で手についた汚れを落とし、激安サイトにアクセスし、ため息混じりにチューブラーをポチッとする。嗚呼…、自転車通勤はエコなのか、それともエゴなのか。私にはもうわからん。
『1Q84 BOOK1~3』 村上春樹 新潮文庫
この本がTVニュースなどで話題になったのはつい最近のことだと思っていたけど、2009年に発売されたとのことなのでもう3年も経ったんだなあと改めて月日の流れの早さに驚く。BOOK1からBOOK3まで、3冊もの超長編(少なくとも私にとっては)が文庫化され、それぞれ上下巻合計6冊となって再販された。BOOK1~2までの上下巻4冊はうまい具合に古本屋で見つけることができたが、BOOK3の上下巻2冊は新品を買った。古本を含むとは言え、一つの物語に2500円前後の大金と、6冊分の読書エネルギーを使ってようやく読み終えた。
世界中で翻訳されてヒットしている本なので、改めてここであらすじを説明する必要もないと思う。私の解釈としては、青豆さんと天吾くんの純愛ミステリーということだろう。そこに宗教やらパラレルワールドなんかが重なってきて、ものすごい広い世界観になっている。今まで何冊か村上春樹の作品を拝読したことがあって、どれもこれも掴みどころが無いというか、明確な解答が無いというか、村上春樹ファンの言葉を借りるならそこには「喪失」しか感じられなくて、どうも肌に合わなかったのだけど、この『1Q84』に関しては「まだマシ」と思える。
丁寧すぎる顔立ちや容姿の描写、音楽やその他芸術に関する詳細な記述、スマートで無駄のない台詞など、まるで伊坂幸太郎を読んでいるような印象だった。でもそれは村上春樹が伊坂幸太郎を真似したのではもちろんなくて、伊坂幸太郎は思いっきり村上春樹に影響されているんだなあと感じた。ていうか結構そこまで真似していいんやねと思ったぐらいである。
ストーリーは非現実的で不思議な方向へだんだんとシフトしていき、いかにも!な村上春樹ワールドへ突入していく。以前の経験から、しっかり読み込んで謎を解けば解こうとするほどワケがわからなくなるという教訓を基に、不思議ちゃんな部分はさらりと読み流す方法でなんとか頁を進めることができた。もっと単純に、もっと素直に、「なかなかすごい比喩やなあ~」とか、「そろそろ濡れ場があってほしいなあ」とか考えながら。
後で知ったことなのだが、実は『1Q84』はBOOK2までで終わりだったそうだ。確かに1と2は同時発行だけど、BOOK3だけは約1年後の発行である。この事実を知ったのはちょうどBOOK3を読み始める頃だった。私は3まであるもんだという心構えで2を読み終えたから良かったものの、もしBOOK2の「あの」シーンで終わりですよと言われたら暴れていたかもしれない。「村上春樹どんだけ~~」である。どんだけ読者に喪失感を与えたら気が済むねんと。
しかし敬虔なる村上春樹信者は文句も言わず、「そうか、春樹さんがここで終わり言うんやから終わりなんや」と受け入れた。もしそうだとしたら、村上春樹の信者になるには相当の「スカシ」にも耐えられる精神力を持たないといけないということである。とにかく村上春樹は約1年というブランクを空け(ワザとだったのか苦情が殺到したのか知る由も無いが)、BOOK3で広がり過ぎた世界をまとめにかかった。そのまとめ役が牛河氏である。
BOOK3は牛河氏のお陰でだいぶ読みやすかった。青豆と天吾を追う探偵役として登場するのだが、2人の過去を洗い直してくれるお陰で、忘れていた背景などを思い出すことができ大変助かった。牛河氏がいなければ、私は未だ釈然としない『1Q84』の世界から抜け出せず、もう二度と村上春樹は手に取らなくなってしまったかもしれない。もしかしたらBOOK3は編集社が強く希望したから完成したのではないかと思うほどのハードルの低さになっていた。それだけ私に貢献してくれた牛河氏はなんとも悲惨な最後となるわけなんだが、6冊(1冊約400頁弱)もの村上春樹ワールドにどっぷり浸かってしまった私は、「はいはい何があっても驚きませんよ」ぐらいにスルーすることができたのである。
6冊である(ひつこい)。6冊もの文庫本が本棚に並んだら結構場所を取るぜ。期間にして約2ヶ月半(読むの遅い)。そんな長い時間村上春樹に触れていると、あの独特の文章にもっと長く触れていたいという気にもなってくる。物語は佳境を迎え、残り頁が少なくなってくると若干の寂しさみたいなものが感じられた。これを信者が言う「喪失感」なのだろうか。物語が終わって感じる喪失感とはなんだか違う心のポッカリ感がある。別に無くても生きていけるけど、無いと寂しいような物足りないような……。
ともあれ、今までは「投げっぱなし感」の強かった村上春樹の作品だったが、この『1Q84』ではだいぶ解釈がしやすかった。村上春樹側が私に合わせてググっとハードルを下げてくれたお陰なのか、はたまた私が月の2つある世界に脚を踏み入れてしまったのか。とあえずまだ1つしか見えない。