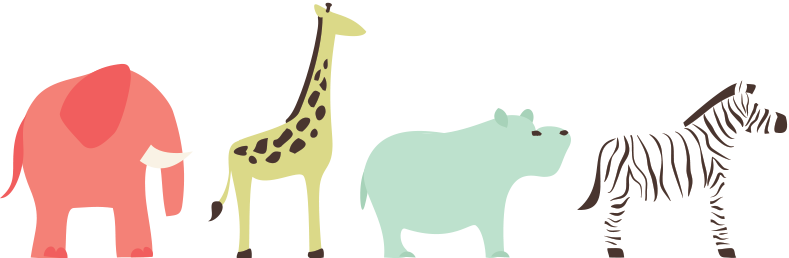以前、夕方の情報番組で湊かなえのロングインタビューがありたまたま観ていたのだけど、なんだか好感の持てるおばさん(失礼w)だったので読んでみた。たしかそのインタビューも夜行観覧車ドラマ化にあたってのものだったと思う。
舞台はとある高級住宅街で、ある一軒の家庭で起こる殺人事件。だけどその犯人が誰なのかとか、何故殺したのかということは二の次で、この物語は家族の絆とか愛とかがテーマ。大きく分けて二軒の家庭の視点から描かれていて、さらにその家族それぞれの視点や感情から、ひとつの物事が説明されていく。
時間軸は間違いなく1本なのだが、それを様々なキャラクターの目線から書かれているので、ひとつの出来事がとても立体的になっている。どのキャラクターがどんな心境なのかを読者が理解しているのに対して、作中の登場人物たちは他人の気持ちが理解できずに思い悩む。そこがまた面白い。
近所付き合い、受験、反抗期、家庭内暴力…。自分のことに置き換えると怖くなってしまうことばかりだが、実は身近に接近している問題ではないかと気付かされるとき、この作中の家族たちが他人には思えなくなって、一気に感情移入、一気に読んでしまった。
登場人物の誰もが何かしらの問題を持っていて、「こいつの言ってることが正解!」ってのがいない。普通のミステリーなら、探偵役とか刑事役が正解を述べるのだが、これは誰が正解というわけではない。だからなんだかスカッとするラストにはならないのかなあと思っていたら、なかなか綺麗にまとめられていて、読後の気持ちよさみたいなのがあった。
湊かなえ作品はこれが初めてだったけど、個人的には宮部みゆきより好きかな。まあ比べるものでもないんだろうけど。
「読書」カテゴリーアーカイブ
『バイバイ、ブラックバード』 伊坂幸太郎 双葉社
ちょっと伊坂幸太郎が自分の中でブームになっている。好きとか贔屓にしているとかそういうのではないけど、一度その文章に慣れてしまったらその作家に対しての予備知識というかそういうものが構築されるので、文章に慣れるまでの時間が割愛される気がして効率よく読めるように思うのだ。
というわけでこの『バイバイ、ブラックバード』。結論からいうと、自分としては伊坂作品の中で一番おもしろかった。主人公の星野は5股もかける女好きなのだが、どういうわけかチャラチャラした女ったらしという感じではなく、どちらかと言うとどんな女性に対しても真面目で一生懸命なところが憎めない。
そして謎の理由で繭実という巨漢の女に連れられて、5人それぞれの女性のところに出向いて別れを切り出すというお話である。なぜ繭実という巨漢の女性に連れられているのか、なぜ5人の女性と別れなければいけないのか、というところはネタバレになってしまうので避けるけど、それぞれの女性の出会いやエピソードが5篇に編集されて大変リズムよく読むことができる。
個人個人のキャラクターが際立っていて、特に星野と常に行動を共にする繭実の存在は大きく、最初はうっとおしいだけのキャラクターだったが、読み進めるうちに、この巨漢女を許容している自分に気づく。それは主人公星野も同じで、理解不能だった繭実の言動を予測できるようになってくる変化は自分のことのようで楽しい。
ラストに向かうまでのストーリーのお膳立てがとてもおもしろいので、否が応でもラストに期待がかかってしまい、このラストは賛否別れるところである。私も正直言ってもう少しその後を読みたいなとは思ったけど、そこは読者の想像に委ねられた。
とにかく星野と繭実のコンビネーションが楽しく、続編があったら読みたいなと思うし、映像化反対とひつこく繰り返している私も、ちょっとこれが映像化されたらどんなんかなーという期待もあったりする。繭実は誰が演ったらいいだろうか。マツコ・デラックス?しずちゃん?北斗晶?想像するだけでもたのしい。
この作品はおすすめです。
『オー!ファーザー』 伊坂幸太郎 新潮社
伊坂幸太郎の新刊。新刊とはいえ2006年に新聞連載として始まったそうで、作品の完成としては『ゴールデンスランバー』よりも前になるとのことだ。まあそんなことはどうでもええか(笑)。
4人の父親と暮らす高校生が主人公。4人の父親は個性豊かで、頭脳明晰キャラ・スポーツ万能キャラ・ギャンブラーキャラ・イケメンキャラである。4人の父親に過干渉にされ辟易する日々。そんな中である事件に巻き込まれ、父親4人が解決に向けて動き出すというようなストーリー。序盤から中盤にかけては主人公の由紀夫と4人の父親、名脇役たちの日常的な会話や出来事がずっと続く。4人父親がいるといっても、誰が本当の父親なのか、母親はどうしてるのかなどの現実的なことは問題ではないようだ。まあ気になるといえば気になるけど、そういう滅茶苦茶な設定が逆に面白い。
序盤中盤でもうそれはありとあらゆる伏線が散りばめられ、終盤も終盤、残り数10頁程度で一気にまとめられる。一気すぎて少々無理やりな感じもするが、伊坂幸太郎はそうなのだ。前にも書いたかもしれないけど、もうそれは見事に丁寧に丁寧に伏線を包み、きちんとオチも用意して、さらにあとがきの部分で自らの物語を解説し、出版にあたっての協力者へのお礼も忘れず、参考文献リストも載せている。きっとめっちゃエエヤツなんだろうなと感じさせる。丁寧で物腰が柔らかく几帳面で勤勉。きっとそんな感じなのだろうなと思っていると、やっぱり伊坂幸太郎に出てくる主人公はみんな伊坂幸太郎キャラなのである。
由紀夫くんも例外ではない。事件に巻き込まれつつも試験のことが気になったり、過干渉気味に接してくる父親や脇役たちを煙たく感じながらも結局言うことを聞いてしまっていたり、返すセリフがクールでユーモアがあったり、出来杉くんな感じである。伊坂幸太郎を始めて読む人にはちょっと違和感がある作品かもしれないけど、痛快な4人のお父さんは楽しい。こんなお父さんたちがいたらさぞかし楽しいだろうなと思う。「いつでも変わってあげるけど?」って由紀夫くんに言われそうだ。
再読シリーズ その2
『イリュージョン』 リチャード・バック
『かもめのジョナサン』と並んで大好きな小説。再読どころか何度も読み返している。正直言って何度も読んでいる割にはあんまり理解しきれていないところがあるのだけれども、なんといっても複葉機の痛快な飛行シーンがサイコーである。
ドナルド・シモダが発する言葉の中にはありがたいものがたくさんあるのだけれども、やっぱり一番好きなセリフは、
「リチャード、全てはイリュージョンなんだよ」
である。『かもめのジョナサン』では、ジョナサンが必死になって飛ぶ訓練をする。そこには世の中の不条理な流れに逆らって生きるかもめの姿が描かれているけど、『イリュージョン』に関しては、もっと楽に、フランクに世の中の不条理を捉え、「世の中なんてイリュージョンさ」と言い放つ、そういう“力の入ってなさ加減”が好きだ。
私も仕事や家庭などで悩むことはあるけど、基本的には深く考えないタイプである。もうすぐ40になるけど、40台というのは20台30台にはできなかった、要らないものの排除や、興味のないことへの無関心が可能になり、肩に力を入れずに楽に生きられる気がしている。『イリュージョン』にはそういう“楽に行こうぜ”という雰囲気が感じられる。
私も20台30台の頃はいろいろと思い悩んだし、かもめのジョナサンみたいに世の中に反発しながら自分の活路を見出したろやんけー!という鼻息の荒さもあったけど、やっぱり「世の中全てはイリュージョンなんだよ~ん♪~(´ε` )」みたいなスタンスで生きていけば、楽なんだ。
みんながみんな、ドナルド・シモダやリチャードみたいに生きられたらいいなとは思う。なかなか難しいだろうけどね。まあ今20台30台の人は、せいぜい苦労してください。バラ色の40台が待ってる…ハズ(笑)。
再読シリーズ その1
『ノルウェイの森』 村上春樹
初めて読んだときはわけも分からず、「春樹ワールドってこんなんなんやー」という感じで終わったが、二度目ともなるとちょっと理解できるようになったと思う。とはいえ、ネットに書き込まれているたくさんの書評を見ると、私の理解なんてまだまだ浅いのだなあと考えさせられることもある。
特に、中学生の課題図書となり、優秀な読書感想文などを読んでいると、自分の文章の稚拙さや、理解の浅さにうんざりすることもある。まだまだ重箱の隅をつつく程度の理解しかしていないようだ。
ワタナベくんは一体何を求めていたのだろうか?直子が完治するのを待って結婚したいみたいなことを言っていたが、なんかそのようには感じられない。19の僕なら迷わず緑に行くだろう。40になった今はレイコさんかな(笑)。どちらにせよ、直子という選択肢はないわー。
たぶんワタナベくんはキズキを求めていたのだろう。あいつは結局バイなのだ。実は自分の中にある「男も好き」という部分に気付かずに、たくさんの女と寝ては哲学的な思想にのめり込み、下半身が暴走する男性的本能に蓋をし続けながら生きていっているのではないだろうか。
とまあ、突拍子もないところで自分を納得させた所で二度目の感想文を終わりにする。しばらく経ってから読み返したら恥ずかしいんだろうな…。
『真夏の方程式』 東野圭吾 文春文庫
ガリレオシリーズ最新作。この6月末頃に映画が公開されて話題になったけど、映像化反対キャンペーン中の私としては活字のほうがやはりいい。とはいえテレビCMなんかで福山雅治とか杏がばんばん出演しているので、どうしても脳内で、湯川学の顔は福山雅治に、そして今回の物語のヒロインである川畑成美の顔は杏になってしまうのである。
しかしまあそれらのキャスティングは、まるで映画が先で小説が後なのかと思うぐらいハマっていて、特に川畑成美の健康的で海が似合いそうな雰囲気は、杏以外に誰が適役やねんというぐらいハマっている。というわけで、登場人物のキャラクターの脳内映像化が簡単で労力を要さなかったために、スッとストーリーの中に引き込まれるような感覚があった。
舞台は夏の海。玻璃ヶ浦(はりがうら)という寂れた観光地の家族経営旅館に湯川学が宿泊することから始まる。同時にこの旅館の家族の親戚でもある小学生、恭平くんも夏休みのために遊びに来ている。湯川学と恭平くんが意気投合し、夏休みの自由研究等の宿題を手伝ったりする場面が微笑ましい。たしか湯川学は子供嫌いのはずだったが、ガリレオシリーズも長期化し、湯川学も子供を許容できるように成長したということなのだろうか。
ある日、同旅館に宿泊していたお客さんが死体で見つかった。事故で片付けようとする地元警察に警視庁から待ったが入り、お馴染み草薙刑事と湯川学の活躍が始まるわけだが、事件の展開的には今までにもないことはなかった展開なので新鮮さはない。実は何年も前に起こった殺人事件が絡んでいて、その秘密が湯川学の頭脳と草薙刑事の捜査によって紐解かれていく。何年も前の事件や出来事が絡んでいるというパターンはガリレオシリーズだけでなく東野圭吾ミステリーズにはよくあるパターンだが、今回の物語は夏の海の美しさや、新鮮で美味しそうな魚介類などが全編に登場するので飽きない。
「家族を守るため」とか「愛する人を守るため」みたいなキーワードが出てくるけど、正直あんまりピンと来なかった。それなら『容疑者Xの献身』とか『麒麟の翼』(これは加賀恭一郎シリーズ)とかのほうがグッとくる。『真夏の方程式』は、奇しくも舞台の美しさが目立ってしまった感がある。だからと言ってはなんだが、映像化反対キャンペーン中の私であっても、映画を観てみたいなあと思ってしまった次第である(笑)。
『夜明けの街で』 東野圭吾 角川文庫
再読。つい最近読んだ気もするし、何年も前に読んだ気もする。子供のスイミング引率の間の暇つぶしに何かいい本はないかなと本棚を漁ったら出てきた。どちらにせよ内容の記憶が無いので、愛用のブックカバーに入れて持ち歩くことに。
ストーリーが思い出せなかったり、感想文の記録が残っていない本は大抵の場合、面白くなかったか読了せずに放置したままになったことがほとんどで、つまりはこの本もそういうことなのだろうと期待せずに読み始めたが、なぜこの本が印象に残らなかったのか、今になって不思議に思う。それぐらい面白くて一気に読んだ。
奥さんと幼い娘との3人暮らし。幸せな毎日なのについ出来心から浮気をしてしまう。それがやがて不倫へと発展し、奥さんとの離婚まで考えるようになる。ところがその不倫相手は実は殺人事件の容疑者だった…という内容。
殺人事件の謎解きがメインとなるような物語ではない。登場人物も少なく、物語の舞台もそう遠くへ飛躍していくようなものではない。とにかく主人公の渡部と、不倫相手の秋葉との恋愛がメインである。不倫関係に陥っていく男の滑稽さが全面に溢れてて、読んでいて苦笑してしまうこともあれば、赤面してしまうこともあるし、ちょっと恐ろしくなったりすることもあった。
別に私が不倫予備軍だと言っているわけではないが、なんだか他人事に感じられないのはやはり自分に少なからずの不倫願望があるからなのだろう。この本は、ヨメに飽きた妄想好きのアラフォー男子に、「そんなアホなことやめとけ」と諭してくるようである。
作中にも不倫に溺れていく渡部に、「そんなことやめとけ」と諭す新谷くんという友人がいるのだが、おまけとして巻末に新谷くんの外伝が収録されている。実は新谷くんもかつて不倫経験者だったのだが、その顛末をわざわざ後に付け足すようにしないで、本編に組み込めばいいのになと思ったけど、これは、ドロッドロの不倫ドラマにしないための作者の照れ隠しなのではないかなと思った。
ミステリー作家である自分が恋愛ドラマを書いているという違和感がそうさせるのか、過去の自分の経験を揶揄するためなのか知る由も無いが、私は勝手に後者だと思っている(笑)。
『R.P.G』 宮部みゆき 集英社
千林商店街の古本屋に100円で売っていたので手に取った。私のとって宮部みゆきは2作目。1作目に読んだ『火車』同様、丁寧な書き方だなと思った。
お父さんが殺され、いろいろと調べていくうちに、そのお父さんはネット上でも「お父さん」を演じ、バーチャル家族ごっこをして楽しんでいたことが発覚。ネット上のお母さん役である女性や、娘・息子役の若者が容疑者として挙げられ、作中のほとんどのシーンはその取り調べ室の中で進んでいく。
はっきり言って、犯人は途中でわかってしまう。「火車」でもそうだった印象があるけど、伏線の張り方なんかがとても丁寧で、はいはいここに手がかりですよ~と言われているかのようだ。もっと乱暴に放り投げるぐらいのほうが面白いと思うのだが、それは宮部みゆきの凄さを分からない私が言うことではないようだ。
この小説の本当の凄さは、犯人が誰かを当てるとかそういうのではなくて、最後のシーンの読者をも裏切る手法である。どんでん返しなんてものではない。あとがきで本人も書いている通り、ある意味ルール違反のようなこの手法は賛否分かれるようで、容疑者たちの丁寧な描写や個性を全面に押し出したセリフの言わせ方など、それら全てが「実は◯◯でした~」と言われたら、「うわ~ヤラレタ~」って言う肯定的な人と、「なんじゃそら」って言う否定的な人に分かれるだろう。
私は正直後者であった。『火車』のときも、最後に「なんじゃそら~」と思ってしまった。こんな裏切り方するなんて、宮部みゆきってなんと性格の悪いオバハンなんだろうか(ファンの方すいません)と思ったぐらいである。しかし、それが宮部みゆきの手法であると知った今、完全に宮部みゆきワールドに飲まれてしまっていた自分に気付くのである。
そういうことも含めて『R.P.G』だとすれば、この作品はすごいと思う。でも、例えばフェラーリのことを「すごい」とは思うけど、乗って楽しいかは別のことであり、フェラーリはフェラーリで認めるし否定も批判もしないけど、私はやっぱりBEETみたいな軽自動車のほうが好きだなあと思うのである。ま、そんな感じ(笑)。
『プリンセス・トヨトミ』 万城目学 文春文庫
国家予算の無駄遣いがないかを検査する会計検査院の3人が、大阪のとある社団法人の検査をすることによって、ものすごい事実に遭遇するというお話し。大阪には「大阪国」なる独立した国家が存在し、大阪国総理大臣や大阪国会議事堂などもある。しかもそれらは大阪の男性のみの中で完全に秘密にされ、豊臣家の末裔である女性を400年も守り続けているという、ぶっ飛んだストーリーである。
壮大なファンタジーという部類に入ると思うのだが、舞台が私のよく知る大阪市内であるので、大阪市内の建物や、大阪人特有の人間性の描写などがやけにリアルに感じられてしまい、ファンタジーとリアルの境界線が自分の中で曖昧になってきちんと物語の世界に身を投じることができなかった。
作者は大阪出身とのことで、かなり大阪を愛しているとみた。さらに細かく取材をしているのがよく感じられる。通天閣の天気予報、大正区の渡し船、「片付ける」を「なおす」と言う大阪弁のくだり、上町台地の坂道、南北を「筋」、東西を「通り」と呼ぶ碁盤の目・・・・。直接ストーリーとは関係ないにも関わらず、これでもか!と言わんばかりに大阪の特徴を紹介してくださるので、大阪人の私にとっては、「もうええやん」ぐらいのお腹いっぱい度合いであった。
あまりにも大阪のことを良いように書くので、逆にこの人は大阪出身ではないのじゃないかと思ったぐらいだ。ほんとに大阪出身なら照れもあってここまで書けないものだと思う。400年もの間に渡って大阪の秘密を守り続けているという設定も無理が感じられる。だいたい大阪の男は「しゃべり」なのである。喋り倒してナンボの大阪人が、400年も秘密を守り続けられるわけがない。この人は本当に大阪のことを知ってるのか?という感じ。「他府県出身だけど大阪が好きすぎて大阪のことをくまなく調べました」的な匂いがするのだ。
最後のストーリーのまとめ方も、ゴリ押し、根性包み、無理矢理感が否めない。大阪人ならオチを大切にするはずなのだが、こんなむりくりまとめにかかったオチにしてしまうなんて、「この人ほんまに大阪の人?」である。逆に大阪人に突っ込みどころを残しておく手法なのかなと思うぐらい。
登場人物の個性あふれるキャラクターの書き分けは上手だなと思った。あとがきにあるエッセイもなかなか良かった。大阪を愛してやまない姿が微笑ましい。しかし作者が「巨人ファン」であることに、少なからずの衝撃を受け、本を閉じました(笑)。
『火車』 宮部みゆき 新潮社
再読。実は従妹に借りて読んだことがあったのに記憶から消え去り、古本屋でついつい手に取ってしまった。読み進めているうちに、「あれ?読んだことある?」となった次第である。初めてこの作品を読んだときは、何が面白いのか理解できなかったけど、今回良くも悪くも再読したことによってその良さがわかった。それだけでも再読の意味があったと思う。
カード破産や、戸籍乗っ取りに関しての記述がかなり詳細で、ちょっとくどい部分もあるにはあるが、クレジット時代に一石を投じる作品だったのだなと思う。しかしそれは重箱の隅をつつくようなことで、本当の面白さは、「犯人が最後まで登場しない」ことだった。
行方をくらませながら逃げ続ける犯人を、追いかける者の目線で書くことにより、犯人像を読者に想像させ、足取りや動機を描いていく。それがとても丁寧で緻密で、読者のほうも「早く犯人に会いたい!」となる。
したがって、初読のときは「なんじゃい!これで終わりかい!」と思ったラストシーンも、再読であった今回は許容することができた。むしろ、このあとに犯人のセリフや描写のシーンがあったとしても、これまで追ってきた刑事の経緯を再び書き連ねるだけにもなりかねない。そんな野暮ったいことをするぐらいなら、スパっと終わったほうが良いのだろう。
宮部みゆき作品は、恥ずかしながらまだ『火車』しか読んだことがないので、ほかの作品ではどんな感じなのか知る由もないけど、文章が女性らしくてとても丁寧だなと感じた。わかりやすいぐらいの伏線がきちんと等間隔に散りばめられ、盛り上がりとクールダウンも等間隔。そしてラストは潔く勇気ある終わり方。いかにも女性らしいと思う。他の作品も読んでみたいと思った。
余談だが、物語の中に大阪球場が登場する。なんばにあった野球場で、取り壊される前は住宅展示場となった。昔、阪神高速環状線を頻繁に走行してたことがあって、そこからいつも見えていた。懐かしい気分になって嬉しかった。