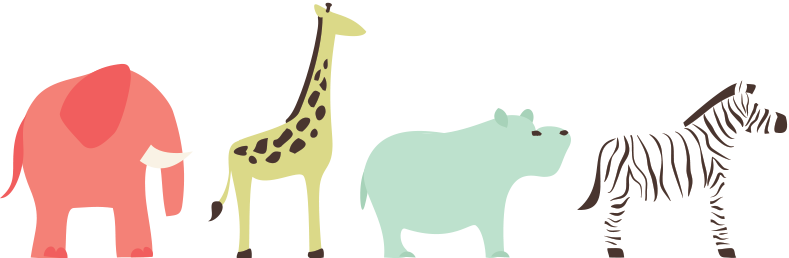以前から少し気になっていたことがある。それは文章を書く上で、自分のことを「僕」と書くか「私」と書くかということである。
子供の頃に「なんでな〜おとなってな〜おとこやのにな〜『わたし』って言うの〜?」というような質問をしたことがある。「大人はみんなそう言うねん」と答えられた。「おとなってなんさい〜?」「20歳や」
今思い出すと非常にめんどくさそうな返答だ。僕はこのことを何故かハッキリ覚えている。だから20歳になったら男性はみんな自分のことを「私」と言うもんだと思っていた。ところがみんなそんなことはしていない。当然僕もしていない。中には「私」と言う人がいるが僕と同じ年齢、世代には少数だ。
まあムリにそう呼ぶことはしなくてもよいと思うので、これからも自分のことは「僕」と言う。きっと「私」を使いたくなる年齢、場所、シチュエーションが来るはずだ。それまで焦らないことにする。
しかし、この日記のような文章を書くときに「僕」を使うのは少し抵抗が出てきた。やはり僕も「オトナ」になってきたということか。
今まで書いてきた僕の文章に表記してある「僕」を「私」に変えて読んでみると(全部読み直したわけではないが)、少し「オトナ」な人が書いたような印象を受ける。支離滅裂で起承転結が無くオチが弱い文章であっても、あたかもそれが「計算の内」という感じさえする。
よし、これからは自分のことを「僕」ではなく「私」と書くことにする。ヘタクソな文章に説得力を持たせようとか、下ネタ系の文に「私」を使うことによって出てくる「逆のおもしろさ」を狙うとか、シタゴコロがないわけではない。
しかし「僕」を「私」に変えることによって自分の「オトナ」意識を高められるんじゃないだろうか。というわけで、これからも私をよろしくお願いします。